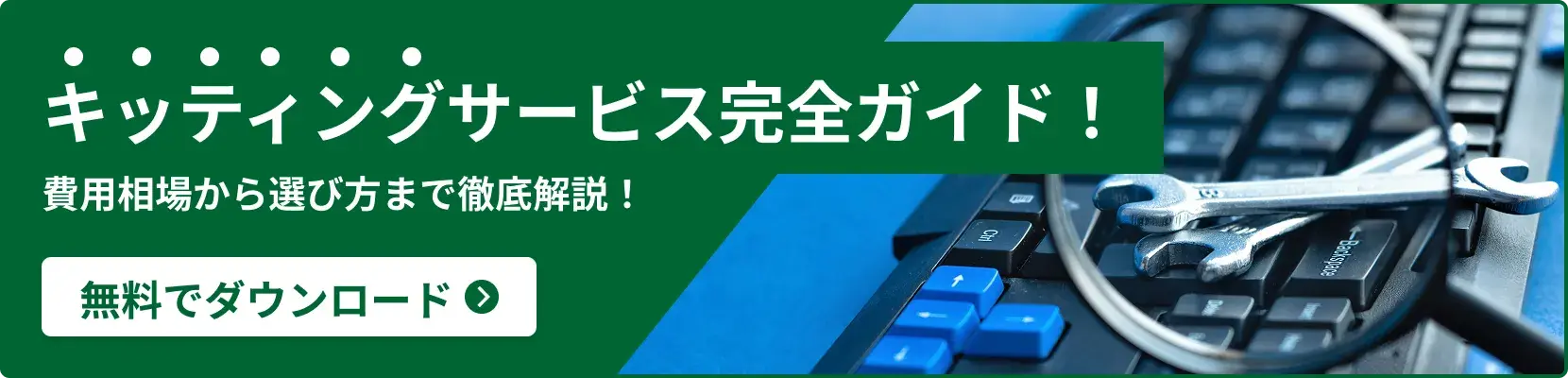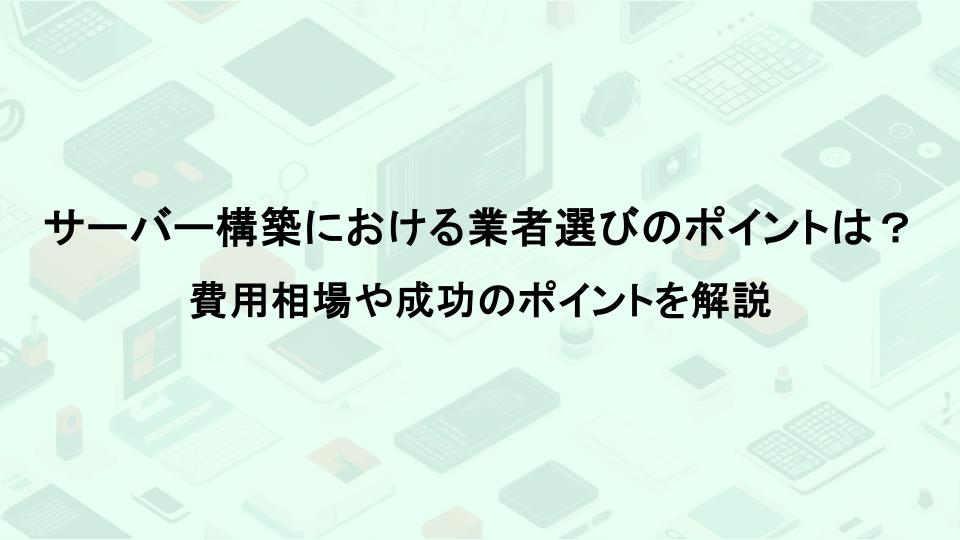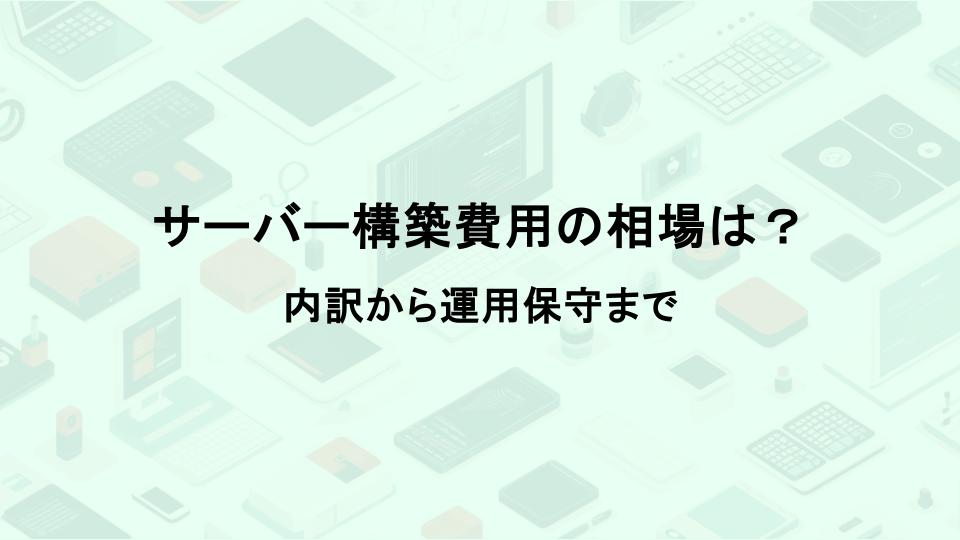記事公開日
デバイス管理とは?企業のセキュリティを強化する方法やツールの選び方を解説
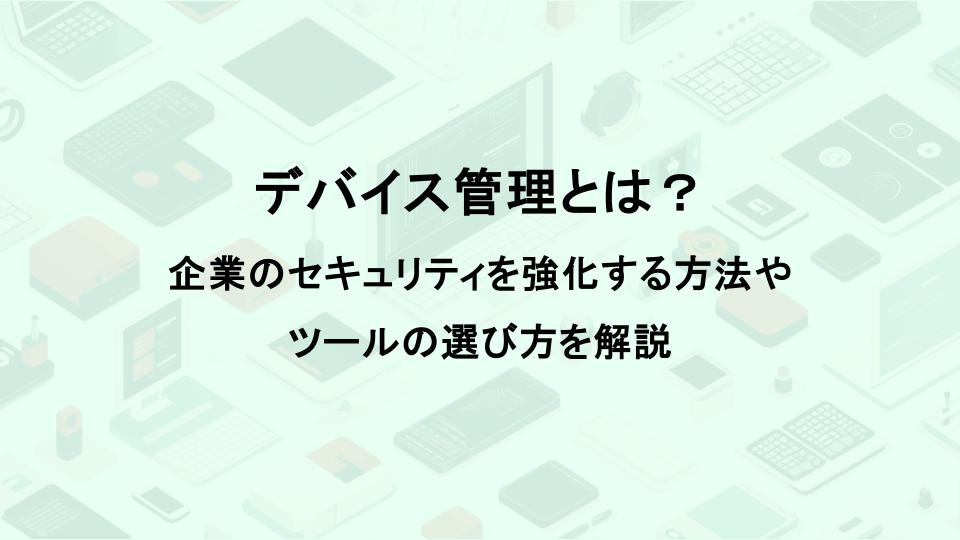
働き方改革やテレワークの普及により、企業が管理すべきデバイスは増加の一途をたどっています。PC、スマートフォン、タブレットなど多様なデバイスが社内外で使用される中、適切なデバイス管理ができていないと、情報漏洩やセキュリティインシデントのリスクが高まります。
本記事では、デバイス管理の基本から具体的な実施方法、ツールの選び方まで詳しく解説します。企業のセキュリティを強化し、効率的なIT資産管理を実現するための実践的な知識を身につけましょう。
関連記事:
MDM(モバイルデバイス管理)とは?主な機能から導入メリットまでわかりやすく解説
デバイス管理とは?
デバイス管理の定義と目的
デバイス管理とは、企業が業務で利用するスマートフォン、タブレット、ノートPC、デスクトップPCといった多種多様なデバイスを、一元的に把握し、設定、セキュリティ対策、運用を行うことです。その主な目的は、情報セキュリティの強化、業務効率の向上、IT資産の最適化、そしてコンプライアンスの遵守にあります。
具体的には、デバイスの登録・削除、設定の配布、アプリケーションの管理、セキュリティポリシーの適用、データ保護、紛失・盗難時の対応などを通じて、企業全体のITガバナンスを確立し、安定した業務環境を維持することを目指します。
企業におけるデバイス管理の重要性
現代の企業活動において、デバイス管理は不可欠な要素となっています。テレワークやリモートワークの普及、BYOD(私物端末の業務利用)の増加により、企業が管理すべきデバイスの範囲は拡大し、多様化しています。これらのデバイスが適切に管理されていない場合、情報漏洩、マルウェア感染、不正アクセスなどのセキュリティリスクが著しく高まります。
効果的なデバイス管理は、これらのリスクを低減し、企業の情報資産を守るための基盤となります。また、デバイスのライフサイクル管理を通じてIT資産を最適化し、導入から廃棄までのコスト削減にも貢献します。さらに、従業員が安全かつ効率的に業務を遂行できる環境を提供することで、生産性向上にも繋がるため、企業の持続的な成長には欠かせない取り組みと言えます。
管理対象となるデバイスの種類
デバイス管理の対象となるデバイスは多岐にわたります。主な種類は以下の通りです。
スマートフォン・タブレット
iOS(iPhone/iPad)やAndroidを搭載したモバイルデバイスで、営業や外出先での業務に広く利用されます。
PC
WindowsやmacOSを搭載したノートPCやデスクトップPCで、社内業務の中心となるデバイスです。
IoTデバイス
センサー、スマートスピーカー、ウェアラブルデバイスなど、インターネットに接続される多様なモノのデバイス。特定の業界や用途で利用されるケースが増えています。
その他
POS端末、デジタルサイネージ、シンクライアントなど、特定の業務に特化したデバイスも管理対象となることがあります。
これらのデバイスは、それぞれ異なるOSや特性を持つため、一元的に管理するためには、包括的な視点と適切なツールが必要となります。
デバイス管理を怠ることで生じるリスク5選
①情報漏洩・データ流出のリスク
デバイス管理を怠ると、企業が保有する機密情報や顧客の個人情報が外部に漏洩する危険性が高まります。例えば、退職者が使用していたPCやスマートフォンからデータが完全に消去されていなかったり、セキュリティ設定が不十分なデバイスが紛失・盗難に遭ったりした場合、これらの情報が悪意のある第三者の手に渡る可能性があります。
情報漏洩は、企業の社会的信用を大きく損ない、損害賠償請求やブランドイメージの失墜といった深刻な事態を招くことになります。
②マルウェア感染・不正アクセスのリスク
管理されていないデバイスは、サイバー攻撃の格好の標的となります。OSやアプリケーションのセキュリティパッチが適用されていない、あるいは適切なセキュリティソフトが導入・更新されていないデバイスは、脆弱性を抱えたまま運用されることになります。
このような脆弱性を突かれてマルウェアに感染すると、デバイス内のデータが破壊されたり、他の社内システムへの攻撃の踏み台にされたりする恐れがあります。また、不正アクセスによって機密情報が窃取されたり、システムが改ざんされたりするリスクも増大します。
③デバイスの紛失・盗難による被害
テレワークやBYOD(私物端末の業務利用)が普及する中で、社外に持ち出されるデバイスの数は増加しています。デバイス管理が不十分な場合、これらのノートPC、スマートフォン、タブレットなどが紛失したり盗難に遭ったりした際に、内部に保存された業務データや個人情報が漏洩するリスクが極めて高まります。
遠隔からのデータ消去やロック機能が設定されていないと、紛失したデバイスがそのまま情報漏洩の引き金となる可能性があります。
④IT資産の把握不足によるコスト増大
企業が保有するデバイスの種類、数、利用状況、リース期限などが正確に把握できていないと、IT資産の適切な管理が困難になります。その結果、不要なデバイスを保有し続けることによる管理コストや電力コストの無駄が発生したり、逆に必要なデバイスが不足して業務に支障が出たりする可能性があります。
また、ソフトウェアライセンスの過剰購入や不足、サポート切れのデバイスを使い続けることによる業務効率の低下やセキュリティリスクの増大も、間接的なコスト増大につながります。
⑤コンプライアンス違反のリスク
デバイス管理を怠ることは、個人情報保護法やGDPR(一般データ保護規則)などのデータ保護に関する法規制や、業界固有のコンプライアンス要件に違反するリスクを高めます。例えば、個人情報の適切な管理体制が整っていないと、法的な罰則や行政指導の対象となる可能性があります。
企業の内部規定や情報セキュリティポリシーが遵守されていない状況は、監査で指摘を受ける原因にもなり、企業の信頼性やレピュテーションに悪影響を及ぼすことになります。
デバイス管理ツール(MDM/EMM/UEM)とは
企業が多数のデバイスを効率的かつセキュアに管理するために不可欠なのが、デバイス管理ツールです。これらのツールは、デバイスの登録から設定、セキュリティポリシーの適用、アプリケーションの配布、さらには紛失・盗難時の対応まで、一元的に行うことを可能にします。主にMDM、EMM、UEMという進化の過程を経て、その機能は拡張されてきました。
MDM(Mobile Device Management)とは
MDMは「Mobile Device Management(モバイルデバイス管理)」の略で、主にスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末に特化した管理ツールです。
企業のモバイル端末やBYOD(私物端末の業務利用)で利用される端末を対象に、セキュリティポリシーの適用、設定の一括変更、アプリケーションの配布・削除、デバイス情報の取得、リモートロックやリモートワイプ(データ消去)といった基本的な管理機能を提供します。
これにより、モバイル端末からの情報漏洩リスクを低減し、紛失・盗難時にも迅速な対応が可能になります。
EMM(Enterprise Mobility Management)とは
EMMは「Enterprise Mobility Management(エンタープライズモビリティ管理)」の略で、MDMの機能を包含しつつ、さらに広範なモバイル業務環境を管理するソリューションです。
MDMがデバイスそのものの管理に重点を置くのに対し、EMMはデバイスだけでなく、モバイルアプリケーションの管理(MAM:Mobile Application Management)や、業務で利用するコンテンツの管理(MCM:Mobile Content Management)、そしてユーザーのID管理(MIM:Mobile Identity Management)といった機能も統合します。
これにより、モバイル環境での業務生産性向上とセキュリティ強化を両立させることが可能になります。
UEM(Unified Endpoint Management)とは
UEMは「Unified Endpoint Management(統合エンドポイント管理)」の略で、MDMやEMMの機能をさらに発展させた、最新のデバイス管理ソリューションです。
UEMは、スマートフォンやタブレットといったモバイル端末に加え、Windows PC、macOSデバイス、Linux、さらにはIoTデバイスなど、企業が利用するあらゆるエンドポイントデバイスを一元的に管理することを目的としています。
OSやデバイスの種類に依存せず、統一されたポリシーでセキュリティ設定、ソフトウェア配布、パッチ管理、資産管理などを実施できるため、多様なデバイスが混在する現代のIT環境において、管理者の負担を大幅に軽減し、セキュリティレベルを向上させます。
各ツールの違いと使い分け
MDM、EMM、UEMは、それぞれ管理対象や機能範囲において違いがあります。
| MDM | モバイル端末の基本的なセキュリティ対策と運用管理が主な目的です。主にスマートフォンやタブレットのみを管理したい企業や、BYODを導入する際の最低限のセキュリティ確保に適しています。 |
|---|---|
| EMM | MDMの機能に加え、モバイル環境での業務アプリケーションやデータのセキュリティ、生産性向上を重視する場合に選択されます。モバイルワークが中心の企業や、より高度なモバイルセキュリティを求める企業に適しています。 |
| UEM | PC、モバイル端末、IoTデバイスなど、企業が利用するあらゆるエンドポイントデバイスを包括的に管理し、セキュリティポリシーを統一したい場合に最適なソリューションです。特に、多様なデバイスが混在する大規模な組織や、ハイブリッドワーク環境を構築する企業、将来的なデバイス増加を見込む企業にとって、管理の効率化とセキュリティ強化に大きく貢献します。 |
これらのツールは、企業の規模、管理対象デバイスの種類、必要なセキュリティレベル、そして予算に応じて最適なものを選択することが重要です。一般的には、MDMからEMM、そしてUEMへと機能が拡張され、より包括的な管理が可能になるという進化の過程を辿っています。
デバイス管理ツールの選び方
管理対象デバイスの種類とOS対応
デバイス管理ツールを選定する際、まず自社で管理したいデバイスの種類とそれらが搭載するOSを明確にすることが重要です。PC(Windows、macOS)、スマートフォン(iOS、Android)、タブレットなど、対象となるデバイスは多岐にわたります。ツールによっては特定のOSに特化しているものや、マルチOSに対応しているものがあります。
例えば、Windows PCが中心であればWindowsに特化した管理機能が充実しているツールが適しているかもしれませんし、従業員がiOSとAndroidの両方のスマートフォンを利用している場合は、双方を包括的に管理できるツールを選ぶ必要があります。将来的なデバイス導入計画も考慮に入れ、幅広いOSに対応しているかを確認しましょう。
必要な機能の明確化
デバイス管理ツールには、インベントリ管理、セキュリティ設定の強制、アプリケーションの配信、リモートロック・ワイプ、位置情報取得など、多種多様な機能が搭載されています。全ての機能が必要とは限らず、過剰な機能は導入コストや運用負荷の増大につながる可能性があります。
自社のセキュリティポリシーや運用体制、解決したい課題を具体的に洗い出し、本当に必要な機能をリストアップしましょう。例えば、BYODを許可している企業であれば、私物端末と業務データの分離機能や、個人情報に配慮した管理機能が求められるでしょう。機能の優先順位をつけ、最適なツールを選びましょう。
既存システムとの連携性
デバイス管理ツールを導入する際、既存のITインフラやシステムとの連携性も重要な選定基準となります。例えば、Active DirectoryやIDaaS(Identity as a Service)といったID管理システム、グループウェア、既存のセキュリティソリューションなどとの連携が可能であれば、ユーザー情報の同期や認証の一元化が図れ、運用効率が大幅に向上します。
連携がスムーズに行われることで、管理者が複数のシステムで重複した設定を行う手間が省け、より統合されたセキュリティ環境を構築できます。導入前に、既存システムとのAPI連携やシングルサインオン(SSO)対応の有無を確認しましょう。
セキュリティレベルと認証方式
デバイス管理ツール自体が、企業の情報セキュリティを支える重要な基盤となるため、そのセキュリティレベルと対応する認証方式は慎重に検討する必要があります。ツールが提供するセキュリティ機能(データ暗号化、パスワードポリシーの強制、不正アクセス検知など)が自社のセキュリティ要件を満たしているかを確認しましょう。
また、ツールの管理画面へのアクセスや、デバイス登録時の認証方式も重要です。多要素認証(MFA)や生体認証、証明書認証など、より強固な認証方式に対応しているかを確認し、自社のセキュリティポリシーに合致する認証方式を選択することで、不正利用のリスクを低減できます。
導入・運用コストの検討
デバイス管理ツールの導入には、初期費用だけでなく、月額または年額のライセンス費用、サポート費用、導入支援費用など、様々なコストが発生します。これらのトータルコストを把握し、自社の予算内で運用が可能かを確認することが重要です。
無料トライアル期間を利用して実際の使用感を確かめたり、複数のベンダーから見積もりを取得して比較検討したりすることをお勧めします。また、コストだけでなく、ツールの使いやすさやサポート体制、将来的な拡張性なども考慮に入れ、費用対効果の高いツールを選ぶことが長期的な運用成功の鍵となります。
キッティングサービスとの連携でさらに効率化
キッティングサービスとは
キッティングサービスとは、企業が従業員に支給するPCやスマートフォン、タブレットなどのデバイスを、業務で利用できる状態に設定する一連の作業を代行するサービスです。具体的には、OSのインストール、初期設定、必要なアプリケーションの導入、セキュリティ設定、ネットワーク設定、アカウント設定などが含まれます。
これらの作業は、特に大量のデバイスを導入する際に企業のIT担当者にとって大きな負担となり、専門的な知識も必要とされます。キッティングサービスを利用することで、IT部門の負荷を軽減し、デバイスを迅速かつ正確に展開することが可能になります。
デバイス管理とキッティングの関係
デバイス管理(MDM/EMM/UEM)は、導入されたデバイスの運用フェーズにおける管理を効率化しますが、キッティングサービスはその「導入初期」に密接に関わります。キッティングの段階で、あらかじめ設定されたセキュリティポリシーや業務アプリケーション、MDMエージェントなどを確実にインストールしておくことで、導入後のデバイス管理がスムーズに移行できます。
例えば、MDMツールに登録するための初期設定や、企業のセキュリティ基準に合致した状態での引き渡しをキッティングサービスが行うことで、デバイス管理の基盤を強固に構築できます。これにより、導入直後から一貫したセキュリティレベルと管理体制を維持することが可能となります。
導入初期の負荷軽減とスムーズな展開
キッティングサービスを活用することで、企業はデバイス導入初期におけるIT部門の負担を大幅に軽減できます。特に、新入社員の増加や大規模なデバイス入れ替えの際には、膨大な数のデバイスを手作業で設定する手間と時間が大きな課題となります。キッティングサービスにこれらの作業をアウトソースすることで、IT部門はより戦略的な業務に注力できるようになります。
また、標準化された手順で設定が行われるため、設定ミスによるセキュリティリスクやトラブルを未然に防ぎ、従業員はすぐに業務を開始できるため、生産性の向上にも寄与します。これにより、デバイスのライフサイクル全体を通じて、導入から運用、そして廃棄に至るまでの一貫した管理体制を効率的に確立できます。
まとめ
本記事で解説したように、テレワークや多様な働き方の普及に伴い、PC、スマートフォン、タブレットといった多様なデバイスをMDM/UEMなどのツールで一元管理することは、企業のセキュリティを維持するために不可欠です。
しかし、これらの管理ツールを効果的に機能させるためには、導入時の「初期設定」が極めて重要です。一台一台のデバイスをMDMに正確に登録し、セキュリティポリシーを適用・徹底する作業は、IT部門にとって膨大な工数と負担になります。
このデバイス管理の「最初の一歩」であるキッティング作業こそ、東信システムサービスにお任せください。
当社は、案件数700件超、数千台規模の導入実績を誇るキッティングのプロフェッショナルです。
最大の強みは、PC(Windows/Mac)、スマートフォン(iOS/Android)、POS、サーバまで、あらゆるデバイスに対応し、お客様のセキュリティポリシーやMDMへの登録作業を含めた「マスタ構築」から「キッティング」までを一貫してサポートできる体制です。
「電源を入れれば直ぐに業務に使える」だけでなく、「導入直後からデバイス管理下にある」状態を実現し、お客様のIT部門の負担を劇的に削減します。デバイスの導入・設定・管理でお困りの際は、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
東信システムサービスのキッティングサービス詳細はこちら
https://www.kittig-toshin-ss.co.jp/about/